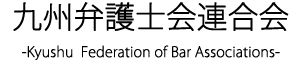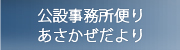全面的可視化と全面的証拠開示を実現する宣言
1 我が国では、これまで供述調書偏重の刑事裁判のもと、密室における違法・不当な取調べが繰り返され、多くのえん罪が生み出されてきた。この数年でも、氷見事件、足利事件、布川事件、厚労省元局長事件、PC遠隔操作事件、袴田事件等、えん罪であることが明らかとなった事件が相次いでいる。当連合会管内においても、2007年(平成19年)2月鹿児島地方裁判所において公職選挙法違反に問われた被告人12名全員に無罪判決がなされた上、捜査機関による組織的な秘密交通権侵害や、親族の氏名等を記載した紙を被疑者の足下に置いて踏ませるという陵虐的な取調べを行ったいわゆる「踏字」につき、国や県の損害賠償責任が認められた「志布志事件」は、未だ記憶に新しいところである。これらのえん罪事件は、いずれも、密室における違法・不当な取調べの実態や、密室では容易に虚偽自白がなされうることを明らかにしたが、上記のうち、氷見、足利、布川、袴田の各再審事件では、再審請求段階において、被告人に有利な証拠が初めて開示され、捜査官による証拠隠しの実態も明らかとなった。これらえん罪事件の経過からみても、違法な捜査を抑制し、えん罪をなくすためには、取調べの録音・録画によって供述のなされた状況を明らかにするとともに、証拠開示手続を法制化して被告人に有利不利を問わず、捜査機関の保管する証拠に被告人・弁護人がアクセスできる権利を保障することが不可欠であることは、明らかである。
2 全面的可視化と全面的証拠開示は、国際的な人権尊重の理念に合致するものである。すでに1998年(平成10年)には、国際人権(自由権)規約委員会は、日本政府に対し、「自白が強要により引き出されることを排除するために、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるべきこと」、「防御権を阻害しないために弁護側がすべての関係資料にアクセスすることができるよう、その法律と実務を確保すること」を勧告している。
取調べの録音・録画も、弁護人が捜査機関の手持ち証拠にアクセスする権利も、多くの諸外国ですでに制度化されており、我が国の法制は立ち後れている。
3 我が国では、2011年(平成23年)6月以来、法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」において、刑事司法制度に関する他の論点と併せて、「取調べの録音・録画」と「証拠開示」について検討がなされ、本年7月に、答申案がとりまとめられたが、その内容は、違法な捜査を抑制し、えん罪をなくすという目的に照らせば、いずれも不十分であると言わざるを得ない。
違法な捜査を抑制し、えん罪をなくすためには、全面的な録音・録画と全面的な証拠開示を制度化し、これによって、刑事司法を徹底的に透明化しなければならない。
4 そこで、当連合会は、国に対し、
(1)取調べの録音・録画については、
- 直ちに、身体拘束下にあると否とを問わず、また、対象事件(犯罪)の種別を問わず、検察官、検察事務官、司法警察職員の被疑者に対する取調べの全過程の録音・録画を義務づけ、これを欠くときは、被疑者の供述調書の証拠能力を否定する法律を制定すること
- 近い将来、被害者、参考人の取調べについても、前項と同趣旨の法律を制定すること
を求め、
(2)証拠開示については、直ちに、
- 全ての通常審手続において、検察官は、被告人または弁護人の請求により、起訴後速やかに、検察官が保管する全ての証拠について、証拠の内容を推知するに足りる事項の記載された証拠一覧表を被告人または弁護人に交付しなければならない。
その後、検察官が新たに証拠を取得した場合、検察官は新たに取得した証拠について、その都度速やかに同様の証拠一覧表を被告人または弁護人に交付しなければならない。 - 検察官は、前項の証拠一覧表を交付した後、被告人または弁護人から同一覧表記載の証拠の開示を求められた場合、直ちに当該証拠を弁護人または被告人に開示しなければならない。
- 再審請求手続においても前項及び前々項を準用する。
- 検察官及び検察事務官は、捜査に関して作成し、取得した証拠を適切に保管しなければならない。
- 司法警察職員は、捜査に関して作成し、取得した証拠を適切に保管の上、その全てを検察官に送付しなければならない。
との趣旨の法律を制定することを求めるとともに、全事件の取調べの全過程の録音・録画と全事件における全面的証拠開示を実現するため、全力を挙げて取り組むことを宣言する。
2014年(平成26年)10月31日
九州弁護士会連合会
提案理由
第1 全面的可視化の必要性とあるべき法制
1 密室における取調べと虚偽自白
我が国の刑事司法制度において、捜査段階における被疑者の取調べは、弁護士の立会いを排除し、外部からの連絡を遮断されたいわゆる「密室」において行われる。そのため、捜査官による威圧、利益誘導、偽計及び詐術等の違法・不当な取調べが行われ、その結果、供述者が意に反する供述を強いられたり、供述内容と異なる虚偽自白調書が作成されることが繰り返されてきた。特に、起訴前の身体拘束期間が長く、起訴前保釈の制度も存在せず、代用監獄が運用される現状においては、捜査機関に対して取調べ時間を厳しく制限する法規制もないままに、供述者が自白するまで身体拘束を容易に解かない、いわゆる人質司法といわれる運用と相俟って「密室」における取調べが虚偽自白獲得及びえん罪の温床となってきた。
1980年代に、死刑確定者に対して、再審において無罪が言い渡された免田事件・財田川事件・松山事件・島田事件のいわゆる死刑再審四事件は、いずれも、当初、虚偽自白に基づいて有罪認定がなされ、無実の者に死刑判決が言い渡された事件である。
捜査段階において、捜査官により供述者から虚偽自白が獲得される事案は決して過去のことではない。最近でも、2000年(平成12年)に松山地方裁判所宇和島支部において、任意取調べにおいて自白した被告人に対して無罪判決が言い渡された宇和島事件、2007年(平成19年)に、鹿児島地方裁判所において、捜査段階で自白した6名を含む12名の被告人全員に対して無罪判決が言い渡された志布志事件、福岡高等裁判所において、任意取調べ中に自白した被告人に対して無罪判決が維持された北方事件、厚労省元局長事件、PC遠隔操作事件など、違法、不当な捜査の結果虚偽自白調書が作成された事件が多数あり、また、氷見事件、布川事件、足利事件、袴田事件の各再審公判においては有罪認定の重要な証拠であった虚偽自白調書がその証拠価値を否定された。このように、長期間・長時間に及ぶ「密室」における違法・不当な取調べの結果、無実の者が虚偽自白に追いやられ、あるいはえん罪被害者とされてしまうという深刻な弊害は、現在も生じている。しかも、取調室が「密室」であるがゆえに、実際にどのような取調べが行われたのか事後的に検証すらできず、根本的な改善が期待できない状況にある。
2 取調べ可視化の必要性
刑事手続における最も重要な目的はえん罪の防止である。捜査段階における全ての取調べを録音・録画する方法により記録すれば、取調べの過程は明らかとなり「密室」における捜査官の供述者に対する威圧や利益誘導等の違法・不当な取調べを防止しえん罪を防止することができる。さらに、記録に基づいた取調べ状況の客観的な検証が可能となり、これまでのえん罪事件の公判で現実に争われてきた供述調書の任意性・信用性を巡る弁護人・検察官双方による攻防も大幅に減少し、裁判の迅速化にも資する。取調べを録音・録画して可視化する要請は、全ての事件の取調べの全過程に妥当することは明らかである。
3 国際人権(自由権)規約委員会勧告と国際的潮流
国際人権(自由権)規約委員会は、1998年(平成10年)、日本政府に対し、「自白が強要により引き出されることを排除するために、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるべきこと」を勧告している。さらに、同委員会は、2008年(平成20年)、日本政府に対し、「取調べに弁護人が立ち会うことが、真実を明らかにするよう被疑者を説得するという取調べの機能を減殺するとの前提のもと、弁護人の立会いが取調べから排除されていること、取調べ中の電子的監視方法が散発的、かつ、選択的に用いられ、被疑者による自白の記録にしばしば限定されていることを、懸念を持って留意する」と、一部録画という手法を批判している。
なお、現実に世界の多くの国、たとえば、イギリスやアメリカの少なからぬ州、オーストラリア、フランス、イタリアなど欧米の多くの国と地域で、取調べの全過程の録音・録画が行われている。またアジア諸国においてもイギリスの法制に通底している香港で可視化がされているのは当然として、歴史的な経緯からわが国の現刑事訴訟法と類似した刑事訴訟法を有する韓国、わが国の旧刑事訴訟法と類似した刑事訴訟法を有する台湾においても、取調べの可視化が実現している。そして、これら取調べの可視化が実現している国・地域においては、捜査官が取調べの可視化を支持しており、取調べを可視化したことによって捜査に支障が生じたという声はほとんど聞かれない。取調べの可視化は、法制度や文化の差異に関係なく導入されるべき、21世紀の刑事司法における普遍的な制度である。
かかる観点からも全ての事件の取調べの全過程について録音・録画が実現されなければならない。
4 全ての事件の取調べの全過程について可視化する意義
(1)被疑者に対する取調べの全過程を可視化しなければならない。
被疑者に対する取調べは逮捕による身体拘束以前の段階から行われる。捜査機関は任意捜査の名のもとに強制捜査の法規制が及ぶ以前の段階においても、被疑者に対して威圧や利益誘導等を行うことにより虚偽自白を獲得してきた。「密室」における取調べの状況を明らかにする取調べの可視化の要請は身体拘束の有無にかかわらず妥当するものである。したがって、被疑者に対する取調べについては身体拘束下にあるか否かを問わず、そして、警察官によるものか検察官によるものであるかを問わず、取調べの録音・録画を実施しなければならない。宇和島事件、北方事件など任意取調べ中に自白した被告人に対し無罪判決が下された事件も任意取調べの過程が記録されていれば、事件の展開は大きく異なったはずである。
従来、検察庁や警察において試行されてきた取調べ終了後の「供述調書の作成場面」を録画したに過ぎない、いわゆる取調べの一部録画では、孤立化して無力感に陥った被疑者が心理的に追い込まれた結果虚偽自白に至る過程が覆い隠されてしまう。一部録画は、「密室」における取調べの弊害を除去することのできない不十分なものである。また、虚偽自白を導いた違法・不当な取調べが奏功した後の「供述調書の作成場面」の可視化は、違法・不当な捜査を正当化する恐れすらある、取調べの可視化とは似て非なるものである。
(2)全事件について取調べを可視化しなければならない。
取調べの可視化の要請は、捜査官の供述者に対する取調べの過程に関するものであるから、特定の犯罪類型に限って要請されるのではなく、捜査官の供述者に対する取調べについては例外なく全ての事件の捜査について等しく要請されるのである。特定の犯罪類型に限らず、全ての刑事事件について取調べの録音・録画が実施されなければならない。
仮に、取調べの可視化を裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件に限定して実施した場合、志布志事件、PC遠隔操作事件等はその対象から外れることとなり、被疑者に対して親族の名前を記載した紙を踏ませることを強要した、いわゆる踏み字事件のような違法・不法な取調べを抑止することは今後も期待できないことになる。
(3)被害者、参考人に対する取調べについても全面的な可視化が必要である。
捜査官の供述者に対する取調べの過程を明らかにしてえん罪を防止しようとする取調べの可視化の要請は、被疑者に対する取調べのみならず、被害者、参考人に対する取調べにも同様に要請される。被害者、参考人に対しても威圧、誘導等の方法による違法・不当な取調べが行われ、これに基づいて被害の内容や状況及び目撃内容や状況について真実とは異なる内容の供述が獲得され、「密室」における違法・不当な取調べによって獲得された被疑者の虚偽自白を支える役割を担わせられることは十分想定できる。被害者、参考人については、捜査官に対して迎合的な供述をする可能性も否定できないのであり、これらの者に対する取調べ状況についても録音・録画する方法により記録して、後日の検証に耐えうる制度を導入することが必要である。
5 法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」の調査審議の結果について
2011年(平成23年)6月以来、上記特別部会の調査審議において取調べの録音・録画制度も取り上げられ、2014年(平成26年)7月には、同部会の調査審議の結果として最終取りまとめがなされた
たしかに、これまで全くの「密室」であった取調室内での取調べ状況を録音・録画する制度が明文化される方向で取りまとめられた意義は小さいものではない。しかし、取調べの録音・録画の必要性や意義に鑑みるとき、その内容は次のとおり極めて不十分と言わざるを得ない。
(1)取調べの客体を身体拘束下の被疑者に限定している。
すでに述べたとおり、多くのえん罪事件で、任意捜査の名のもとに身体拘束されていない被疑者に対する違法・不当な取調べが行われ、虚偽自白が引き出されたことを忘れてはならない。
(2)対象事件を裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件に限定している。
当該対象事件が、公判請求される事件に占める割合は、2ないし3パーセントと言われており、取調べの録音・録画に期待されるえん罪防止の効果が及ぶ範囲は極めて限定的である。かろうじて厚労省元局長事件については、当該対象事件に含まれるが、志布志事件、PC遠隔操作事件、いわゆる痴漢えん罪事件等については対象外とされる。もとより、当該対象事件にのみ取調べの録音・録画による可視化の要請が限定される理論的な根拠は存在しない。取調べの録音・録画の必要性は重大事件に限って妥当するものではない。法定刑の比較的軽い事件こそ長期の身体拘束を避けるために虚偽自白をする危険が高い。全ての事件を録音・録画の対象とすべきことは明らかである。
(3)抽象的な基準による広範な例外事由が認められている。
このような例外事由の定め方は、上記特別部会の議論の過程で否定された取調べの録音・録画の実施を捜査側の裁量にゆだねる考え方と変わらない運用を招きかねない。
6 最高検察庁の依命通知について
今般、最高検察庁は、「取調べの録音・録画の実施等について(依命通知)」と題して従来の取調べの録音・録画の試行を終了し、2014年(平成26年)10月1日から対象事件を限定した録音・録画の実施と従来の試行対象事件以外の身体拘束事件の被疑者及び被害者・参考人に対する取調べの録音・録画の試行を通知した。これについて、検察庁による取調べの録音・録画の実施範囲の大幅拡大との報道もあった。
しかし、検察庁の取調べの録音・録画の実施は供述の任意性や信用性等に関する立証責任を的確に果たすことに主眼が置かれており、取調べの録音・録画の実施及びその対象について検察官の裁量を前提としている。また、取調べの録音・録画の試行も、供述の任意性・信用性等の的確な立証に資するよう、事案に応じて、取調べの全過程の録音・録画も含め、様々な録音・録画を試みるものとして録音・録画の有効性及び問題点等について多角的な検証を実施することがその趣旨とされている。すなわち、「密室」における取調べの過程を明らかにしてえん罪を防ぎ、違法・不当な取調べを防止するという取調べの可視化の本来的な目的とは異なる観点から実施、試行されるものである。
捜査機関の裁量に基づいて実施される録音・録画は、取調べの状況を第三者によって検証できるようにするという「可視化」の本来の意義に合致せず、可視化の名に値するものではない。
7 あるべき法制化
「密室」における違法・不当な取調べを防止し根本的に虚偽自白及びえん罪を防止するためには、
(1)刑事事件の被疑者に対する取調べの録音・録画については、裁判員裁判対象事件や検察独自捜査事件などという対象事件の種別を問わず、全事件についての実施が不可欠である。さらに、被疑者について強制捜査以前の任意捜査の段階で違法・不当な取調べが行われうることを考えれば、被疑者について身体拘束がなされているか否かにかかわらず実施されるべきである。また、その取調べの全過程が録音・録画されることが不可欠であり、弊害すら生じかねない一部の可視化は許されない。以上の内容での取調べの全過程の録音・録画を検察官、検察事務官及び司法警察職員に対し、義務付け、当該義務違反がある場合、被疑者の供述調書の証拠能力を否定する法律を制定することが必要である。
(2)さらに、近い将来、被害者、参考人の取調べについても、被疑者におけると同様、その全過程の録音・録画を検察官、検察事務官及び司法警察職員に対し、義務付け、当該義務違反がある場合、被害者・参考人の供述調書の証拠能力を否定する法律を制定することが必要である。
第2 証拠開示の必要性とあるべき法制
1 えん罪事件の発生と証拠開示の必要性
わが国の刑事訴訟法においては、捜査機関が保有する証拠の全面的な開示を求める権利が被告人、再審請求人、弁護人(以下「弁護側」という。)に認められておらず、どのような証拠を開示するかは基本的に検察官の判断に委ねられているため、否認事件など証拠開示が切実に求められる事件において、検察官が証拠開示を強固に拒否する例が後を絶たない。また捜査機関の不当な証拠隠しが横行し、これにより幾多のえん罪事件が発生する事態に至っている。
過去の裁判例を見ても、布川事件、松山事件、免田事件、財田川事件、梅田事件、徳島事件、福井女子中学生殺人事件、足利事件、東電OL殺人事件、袴田事件など、再審請求段階において初めて開示された証拠が決め手となって再審開始、無罪に結びついた事件は枚挙に暇がない。果ては、2010年(平成22年)に無罪判決が言い渡された厚労省元局長事件において、検察官が、公訴事実との矛盾を隠蔽するため、証拠の一部を改ざんしていたことが、証拠開示を通じて明らかになった。
これらは、無辜を処罰する過ちを犯さないためには証拠開示が必要不可欠であることを、貴重な教訓として示している。
2 証拠開示についての最高裁昭和44年決定
そもそもわが国の刑事訴訟法は、2004年(平成16年)の刑事訴訟法改正によって導入された公判前整理手続における証拠開示制度の導入以前は、証拠開示に関する規定を欠いていた。
ようやく最高裁が、昭和44年4月25日決定において、証拠調べに入った後であるものの、「具体的必要性を示して、一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がなされた場合、事案の性質、審理の状況、閲覧を求める証拠の種類及び内容、閲覧の時期、程度および方法、その他諸般の事情を勘案し、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅、証人威迫の弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、その訴訟指揮権に基づき、検察官に対し、その所持する証拠を弁護人に閲覧させるよう命ずることができるものと解すべきである」と判示した。
検察官が有する証拠の個別開示については以前から様々な場面で争われていたが、上記最高裁決定をきっかけとして、裁判所の訴訟指揮権の発動によってそれまで検察側が頑なに拒否していた手持ち証拠の個別開示が認められるようになった。
しかし、条文の根拠がない中で、例外的、限定的に認められた「運用」であって、しかも公判において証拠調べの段階に入った後という審理の終盤の段階でしか認められず、さらに個別具体的な証拠を被告人、弁護人が特定しなければならなかったため、当然ながら被告人の防御権を十全ならしめるための証拠開示とはほど遠いものであった。
3 公判前整理手続等における証拠開示制度
その後、刑事訴訟法は、2004年(平成16年)の改正により公判前整理手続及び期日間整理手続(以下「公判前整理手続等」という。)に付された事件における被告人、弁護人の証拠開示請求権を定めた。
しかし、そもそも被告人に有利な証拠の隠匿から生じる「えん罪」を防ぐためには、被告人,弁護人に対する証拠開示は、公判前整理手続等に付された事件に限ることなく、全ての事件においてなされるべきである。特に裁判体の裁量で公判前整理手続に付されるか否かが判断されている実務を前提にすればなおさらである。
また、公判前整理手続等に付された場合でも、現行の証拠開示制度はいまだ不十分である。
そもそも被告人、弁護人には、捜査機関がどのような証拠を作成又は入手したかを知る手がかりがない。
さらに、被告人、弁護人に開示請求権が認められる証拠は、法316条の15第1項(類型証拠開示)又は同法316条の20第1項(主張関連証拠開示)の要件に該当するものに限られており、捜査機関が保有する証拠の存在が分かったとしても、「類型証拠・主張関連証拠に該当しない」と検察官が判断すれば、被告人に有利な証拠が開示されない結果となりかねない。
特に厚労省元局長事件においては、改ざんした検察官とは別の公判担当検察官が、その改ざんの事実を知らず、改ざん前の捜査報告書を弁護人に任意開示したことで、弁護人が改ざんに気づいたものであって、その公判担当検察官が改ざんの事実に気づき、当該改ざん前の捜査報告書を「類型証拠、主張関連証拠に該当しない」と判断していれば、改ざんの事実も明らかにならず、元局長が有罪とされた可能性は高い。そうだとすると、現行の類型証拠開示、主張関連証拠開示だけでは、えん罪は防止できないことは明らかである。
4 全面的証拠開示の必要性
そもそも検察官は、公益を代表する者であり(検察庁法4条)、その訴訟活動は、単に被告人の有罪を求めるだけではなく、実体的真実の究明を目指した公正なものでなくてはならない。
警察または検察が、強大な組織として捜査権限を付与され、税金という公費によって証拠を収集することができるのは、検察官の公益の代表者としての職責の故であり、捜査機関が法律に基づいて公費で収集した全ての証拠は、公正な刑事裁判を実現するための公共の財産というべきである。
しかして、証拠開示請求権は、弁護側の有する基本的な権利である。弁護側において、検察官が証拠調べを請求した証拠の内容を吟味し、相手方当事者としてこれらの証拠に対する弾劾を行うことは、憲法上保障された(憲法31条、37条1項、2項)被告人の防御権の行使である。そして被告人が防御権を十分に行使するためには、弁護側に捜査機関が入手した全ての証拠を検討できるようにすることが必要不可欠である。
5 国際人権(自由権)規約委員会勧告と国際的潮流
(1)国際人権(自由権)規約委員会勧告
国際人権(自由権)規約委員会は、1998年(平成10年)11月に、日本政府に対し、「委員会は、刑事法において、検察官には、公判において提出する予定であるものを除き捜査の過程で収集した証拠を開示する義務はなく、弁護側には手続の如何なる段階においても資料の開示を求める一般的な権利を有しないことに懸念を有する。委員会は、規約第14条3項に規定された保障に従い、弁護を受ける権利が阻害されないよう、締約国がその法律と実務を、弁護側がすべての証拠資料にアクセスすることが保障されるように改めることを勧告する」と述べて、日本も批准している国際人権(自由権)規約14条3項が、捜査機関が収集した防御に必要な証拠の全ての開示を受ける権利を保障していることを前提として、弁護側に全面的な証拠開示請求権を保障するよう求めている。
(2)諸外国における証拠開示法制
- カナダにおいては、公判前における検察官の全面的証拠開示義務を承認したものとして、1991年のスティンチコム事件のカナダ最高裁判決(スティンチコム判決)がある。
スティンチコム判決では、検察官の開示義務に関して、(1)当事者主義訴訟での不意打ちの防止、(2)刑事訴追の目的は有罪判決の獲得にあるのではなく犯罪と主張される事実に関する証拠を公判に提出することにあること、(3)検察の手中にある捜査の成果は有罪を確保するための検察の財産ではなく、正義がなされることを確保するために用いられる公共の財産(the property of the public)であること、を理由に公判前における検察官の全面的証拠開示義務を承認した。また、開示対象、時期については検察側が利用を予定する証拠、証人に限らず、有罪証拠、無罪証拠の区別なく、全ての関連する物(情報)に及ぶとし、開示請求は起訴後何時でも行えるが、検察側は請求を受けた場合、意思決定のために被告人が情報を考慮する十分な時間的余裕を与える必要もあるとした。そして、開示による弊害については、検察側に対して、開示対象と開示時期に関する裁量を承認する一方、不開示裁量については、裁判官による審査がなされるべきとした。
カナダでは、さらに不開示に対する救済としては、(1)公判延期、(2)手続打ち切り、(3)再審理、(4)証拠排除の各類型が事例として集積されている。 - アメリカにおいては、1963年のブラッディ判決が、検察官には無罪方向の証拠、罪責軽減証拠を適時に開示する憲法上の義務があることを判示した。連邦検察官職務マニュアルにおいては、これらの証拠については弁護側の開示要求がなされるか否かにかかわらず開示されなければならないこととなっている。
- イギリスにおいては、判例法上、手続に濫用状態(abuse of process)が存在する場合には、例外的に、手続打ち切り(stay of proceeding)が行われることが認められている。公正な証拠開示を受ける被告人の権利は、公正な裁判を受ける権利と不可分と捉えられており、証拠の不開示についても、手続濫用を構成しうるというのが裁判所の立場となっている。
- オーストラリアにおいては、バリスターの倫理規定において「検察官は、以下の(弊害がある)場合を除いて、検察官に知られているか、あるいは、検察官が被告人の有罪や無実に関連する資料となると気づいている、あらゆる資料-そうした資料に結びつく可能性のある潜在的な証人の氏名も含む-をできる限り速やかに対立当事者に開示しなければならない」と定めている。
- ドイツにおいては、ドイツ基本法103条1項(裁判所において法的聴聞を請求する権利を保障)、およびヨーロッパ人権条約6条1項(公正な手続を請求する権利を規定)により、刑事手続の全ての段階において、被疑者・被告人の証拠開示請求権に憲法的価値が認められている。この憲法的価値を実現すべく、ドイツ刑訴法147条1項は「弁護人は、裁判所に存在する書類または公訴提起の際に提出されるであろう書類を閲覧し、そして、職務上保管されている証拠を閲覧する権利を持つ」と規定する。これにより、弁護人は、(1)裁判所に存在する書類、(2)公訴提起の際に提出されるであろう書類、 (3)職務上保管されている証拠を閲覧することができる。
- EUでは、欧州評議会による「検察官の役割に関する勧告」29条で、検察官には弁護人への情報開示を通した武器平等を実現する義務があることを明らかにし、客観義務を承認している。この勧告に基づいて2005年のブダペストガイドライン(検察官倫理と行動に関する欧州ガイドライン)が策定され、その中で、情報(証拠)開示により検察・弁護側の武器平等という価値を実現することが倫理的義務として明記されている。
6 法制審議会「新時代における刑事司法制度特別部会」における検討状況及び答申案
前述したこの間の捜査機関による証拠隠しや改ざん事件の発生等を受けて、証拠開示の機運が高まり、上記特別部会では、新たな証拠開示制度について議論がなされた。
結果として、証拠開示制度について、証拠一覧表の交付制度が認められた点は評価できる。被告人、弁護人は、証拠開示請求の前段階において、証拠についての「手がかり」を得ることができ、その後の開示請求に対する開示が適切に行われれば、被告人、弁護人が必要とする証拠へのアクセスが実現できるからである。また、捜査機関によってどのような証拠が作成又は入手されたかをチェックする機会が与えられることによって検察官による証拠隠しや証拠の存否を巡る紛糾を一定程度防止することが期待できる。
しかし、事件対象は公判前整理手続に付されたものに限られる上、あくまでも、証拠一覧表に記載された証拠の開示は、公判前整理手続の枠組みの中で、「類型証拠」、「主張関連証拠」に該当するものについてしか認められないこと、一覧表に記載されている証拠が全ての証拠であることを担保する仕組みがなく、「捜査に支障が生ずるおそれ」などがあると検察官が判断した場合は、その一覧表さえ開示しなくてもいいとされており、結局、証拠開示は検察官の裁量によって大きく左右される結果となっていること、警察が保管する証拠は対象外とされていること、再審事件は「今後の課題」とのことで具体的に考慮されていないことなどから、証拠開示制度として甚だ不十分であることは多言を要しない。
7 あるべき証拠開示制度
既に述べたとおり,被告人,弁護人に対する証拠開示手続は、公判前整理手続等に付された事件に限ることなく全ての事件において制定されるべきであることは前提であるが,さらに全面的な証拠開示を担保するために,以下の諸点につき,あるべき制度を述べる。
(1)証拠一覧表の交付制度について
- 全証拠の一覧表であるべきこと
検察官による証拠一覧表の交付が一定の意義を有することは既に述べたとおりである。
また、公判前整理手続において裁判所が検察官に提示を命じることができる一覧表に記載されるべき証拠の範囲について、「検察官が保管する証拠」と定めているが、証拠の廃棄や還付等による証拠開示逃れを防止するためには、検察官が「現に」保管している証拠に限らず、当該事件の捜査の過程で作成・入手した全ての証拠が一覧表に記載されるべきである。 - 証拠一覧表の記載事項について
前述のとおり、証拠一覧表の意義は、証拠開示請求の「手がかり」となり、弁護側が必要とする証拠へのアクセスを実現することにある。この意義に照らすと、証拠一覧表には、証拠の内容が推知できる程度の事項が記載されなければならない。例えば、検証の結果や鑑定の経過及び結果を記載した書面については、証拠の標目、作成者の氏名及び作成年月日のみならず、それぞれ、検証対象物、鑑定資料及び鑑定事項の記載が必要である。
上記のような項目の記載を求めても、その作成によって捜査機関に過重な負担を課すものではない。
(2)警察から検察への全証拠送致義務について
さらに、検察官が作成・入手した全ての証拠について全面的な証拠開示がなされるとしても、警察が、その作成・入手した証拠を、つまみ食い的に検察官に送致するとすれば、やはり弁護側に有利な証拠が隠される余地が生まれることになる。
特に、捜査の第一次的な担い手である警察でこそ、初動捜査で集められた供述や客観証拠などの中に、弁護側に有利な証拠が作成されている可能性がある。そして、警察が作成・入手した証拠も、すべて「公費」を投じて刑事裁判という国の制度に資するために作成・入手されたものであるから、全証拠が、検察官に送致されるべきである。
(3)証拠の保管義務について
仮に証拠一覧表の開示がなされるようになったとしても、証拠一覧表は個別証拠開示の前提であり、各個別証拠が、その開示の時まで捜査機関によって適切に保管されなければ、結局個別の証拠が適切な形で弁護側に開示されないので、意味がない。
つまり、捜査機関が作成・入手した証拠に適切な保管義務が課されなければ、その後に行なわれる全面的証拠開示につながらない。
(4)再審における証拠開示について
確定判決を検証し、無辜を救済するという再審の目的に鑑みれば、再審手続においてこそ、全面的な証拠開示が果たされるべきである。
冒頭で述べたように、過去の幾多の再審請求事件において、捜査機関が保有していた「古い」証拠が、証拠開示によって明るみになることで、再審開始・無罪が掴み取られたという事実は、それを如実に表している。誤判の疑いのある過去の確定判決を検証するためには、捜査機関において作成・入手した証拠の全てが白日の下にさらされる必要がある。確定有罪判決を支えていた証拠構造について、新証拠のみならず、捜査機関が保有していた(被告人に有利な証拠も含めた)その余の全ての証拠群によって弾劾されてもなお、有罪の判断が維持できるかが問われるべきだからである。
鹿児島の大崎町で起きたいわゆる「大崎事件」においては第2次再審請求即時抗告審において弁護人の請求により、検察官から213点もの未開示証拠が、事件から34年ぶりに開示された。その証拠開示は、即時抗告審決定において(結論としては棄却であったが)、それら「新」証拠の証明力によって、「実行犯」とされた者らの自白供述の信用性が「それ自体だけからでは決して高いものとはいえない」と言わしめた。
上記即時抗告審の原審である鹿児島地裁の再審請求審では弁護団の証拠開示請求が一顧だにされなかった。このように再審請求における証拠開示は、各裁判体ごとの判断が区々になっている。
従って、裁判体ごとの格差を許さない全面的証拠開示の法制化が必要であることは明らかである。
なお、証拠開示に伴う弊害を理由に反対する意見もあるが、再審請求段階においては、確定前に比して、証拠開示に伴う弊害(プライバシー侵害、罪証隠滅等)のおそれは、格段に低くなっており、開示にともなうデメリットも小さい。
(5)捜査機関に対するサンクションの必要性について
上記、検察、警察に対する義務を実効的に果たさせるためには、その不履行の際の制裁措置が必要不可欠である。
前述のカナダの例を参考にすれば、捜査機関が十分に証拠開示を行わなかったことが明らかになったときは、公判の延期や再審理、そして当該事件の公訴を棄却し、刑事手続を打ち切るといった、強い制裁措置も考えられる。
えん罪が極めて過酷な人権侵害であることに鑑みれば、捜査機関が、被告人に有利な一部の証拠を隠して有罪判決を獲得するようなことは1件たりともあってはならないからである。
ただ、実効性があり、かつわが国の刑事訴訟制度にふさわしいサンクションのあり方については、なお、検討の必要があると思われる。
第3 結語
よって、当連合会は、国に対し、取調べの録音・録画及び証拠開示について、それぞれ、上記「宣言」(案)記載のとおりの法律を制定することを求めるとともに、今後、決して歩みを止めることなく、個別事件における弁護実践や、法制化に向けた提言・運動を通じて、全事件における取調べの全過程の録音・録画と再審請求も含めた全事件における全面的証拠開示を実現すべく、全力を挙げて取組むことを宣言する。
以上