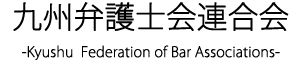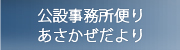現在の再審制度の問題点を踏まえ、再審に関する法整備を行うことを求める決議
当連合会は、現在の再審制度の問題点を踏まえ、以下のとおり国に対して再審に関する法整備を行うことを求める。
1 国は、刑事訴訟法の再審制度に関する法律を整備し、
(1) 有罪判決確定後に、再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者又はこれらの者の弁護人から、検察官に対して、検察官が保管する公判未提出証拠の開示請求があったときは、検察官は再審請求の申立前であっても、検察官が証拠開示に応じることを義務づける証拠開示法制度を創設すること
(2) 再審請求審において、請求人又は弁護人から証拠開示請求がなされたときは、裁判所は、特別の事情がない限り、検察官に対して、開示請求がなされたすべての証拠について開示に応じるよう勧告することを義務づける証拠開示法制度を創設すること
(3) 再審請求審において、検察官は、捜査機関が保管するすべての公判未提出証拠について記載した証拠目録を作成し、その証拠目録を請求人又は弁護人に開示する法制度を創設すること
(4) 再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者又はこれらの者の弁護人から再審請求の意向を示されたときは、検察官は、確定審において提出された証拠のみでなく、未提出の証拠についても保存すべき法制度を創設すること
2 国は、
(1) 再審請求中に本人が死亡した場合の承継手続に関する法制度を創設すること
(2) 再審開始決定に対する検察官の不服申立禁止の規定を定める改正を行うこと
3 国は、
再審開始決定が確定し、再審無罪となった事件については、独立して誤判原因を検証する第三者機関による検証委員会を速やかに設置すること
以上のとおり、決議する。
2019年(令和元年)10月25日
九州弁護士会連合会
提案理由
第1 再審制度の現状と問題点
1 再審制度の現状
1985年(昭和60年)1月6日に発生したとされた殺人事件である松橋事件では、元被告人は懲役13年の有罪判決を受けて服役した後、再審請求を行い、34年間の年月を経て、本年(2019年)3月28日に再審無罪判決が出され、即日確定した。
また、松橋事件以外にも、九州では大崎事件を初め、飯塚事件など複数の再審請求事件が係属しており、冤罪を主張して現在も争われている。九州以外でも、昨年(2018年)には、大津地方裁判所において日野町事件で再審開始決定がなされ、検察官の即時抗告により、現在大阪高等裁判所に係属している。また、本年(2019年)3月18日、湖東事件について、大阪高等裁判所の再審開始決定に対する検察官の特別抗告が最高裁で棄却され、再審開始決定が確定し、再審公判を開始することが確定している。
このような現状に対しては、かつて開かずの門とされた再審について、司法は再審開始の方向で動いているという評価も可能である。しかし、死刑事件である袴田事件では、第一審の静岡地方裁判所で出された再審開始決定が、昨年(2018年)東京高等裁判所で取り消され、再審請求が棄却されたため、現在最高裁判所に係属中である。また、大崎事件では、鹿児島地方裁判所、福岡高等裁判所宮崎支部の再審開始決定に対して、検察官が特別抗告を行い、その後最高裁判所に1年3か月もの長期間係属していたが、本年(2019年)6月25日、最高裁判所は再審決定を取り消し、再審請求を棄却した。このような現状からすれば、再審の道は、今なお遠いというのが実情である。
今年度の日本弁護士連合会の人権擁護大会でも、再審問題がテーマの一つとして取り上げられる。さらに、国会でも、再審法の改正をめぐって、国会議員による議論が始まっている。今後の再審に関する法整備は緊急の課題であると言っても過言ではない。
このように、再審制度の現状と、この間の再審開始決定をめぐる弁護活動によって明らかとなった現在の再審制度の問題点を踏まえ、再審に関する法整備を求めるためにも、当連合会の大会において決議を行うことは極めて重要な意義があるものである。
2 現在の再審制度の問題点
(1) 新たな証拠を収集・発見することの困難性
一旦有罪判決がなされ、最高裁判所にまで争われたにもかかわらず有罪判決が確定した事件について、確定判決の誤りを主張して再審請求を行い、無罪判決を取得するのが至難の技であることは言うまでもない。再審が認められるためには、確定判決に事実認定の誤りがあるというだけでは足りず、確定判決の事実認定の誤りを覆すための明白な新たな証拠が必要である。しかしながら、刑事事件の証拠は捜査機関が独占しており、弁護人は捜査機関が有している証拠を覆すような証拠を有していないのが一般的である。
まして、一旦確定した有罪判決の事実認定を覆すような新たな証拠を収集・発見することは困難を極めるものである。このような実情を考えると、再審制度を考えるに当たっては、証拠開示の必要性が極めて大きい。
(2) 再審手続の長期化による弊害
有罪判決が確定した後に、その冤罪を主張して再審の準備を行っても、再審請求を行うに至るまでも莫大な時間と労力を要することになる。松橋事件でも1990年(平成2年)に最高裁判所で有罪判決が確定し、1992年(平成4年)から再審の準備を行ったが、実際に2012年(平成24年)に再審請求を行うまで実に20年間を要している。
また、最高裁判所で再審開始決定が確定したのは昨年(2018年)10月10日であり、再審請求を行ってから再審開始が確定するまで6年半もの年月を要した。
さらに、再審請求審で再審開始が一旦認められても、その後の検察官の即時抗告等により再審開始決定が上級審で争われる中で、元被告人が高齢化の影響で体調を崩したり、途中で死亡したりしてしまうことも考えられるのであり、再審に時間がかかりすぎることは弊害が大きい。
第2 証拠開示制度の法制化の必要性
1 再審請求前における証拠開示の必要性
松橋事件では、自白において「凶器に巻いた後燃やした」とされていた布が、再審請求を行った2012年(平成24年)よりも15年前の1997年(平成9年)の時点で、検察庁に保管されていたことが分かった。これは、検察官が弁護人に証拠物の閲覧許可をしたことによって発覚したものであるが、この証拠の発見こそが再審開始決定に決定的な影響を与えたのである。
しかし、再審請求前の証拠開示については法律で明文化されておらず、検察官から個別に閲覧許可を得るという方法しかない。そのため、検察官次第で対応にばらつきが出る可能性があるし、検察官の裁量に委ねてしまうと閲覧請求を拒否する対応となる可能性が高い。
特に再審請求前の証拠開示については、必要に応じて証拠開示が実現される仕組みを作る必要があり、そのことが再審開始への道筋を大きく広げるものであると言っても過言ではない。
それゆえ、有罪判決確定後に再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者又はこれらの者の弁護人から、検察官に対して、公判未提出証拠の開示の申出があったときには、検察官は再審請求の前であっても、証拠開示に応じることを義務づける証拠開示法制度を創設すべきである。
2 再審請求後の証拠開示
再審請求後に、まず行うべきは証拠開示である。しかし、検察官は、弁護人の証拠開示の請求に対して極めて消極的な姿勢をとり、再審請求審は当事者主義ではなく職権主義であると主張し、弁護人の証拠開示の請求に応じる義務はないとして、証拠開示を拒否しようとするのが一般的である。
また、再審請求後の証拠開示の可否については、裁判官の訴訟指揮に委ねられており、弁護人もいかに裁判官を説得して検察官に対して積極的に証拠開示を行わせるかに多大の労力を費やすことになる。
しかし、裁判官によって、その対応に差があることは紛れもない事実である。大崎事件の第2次再審請求審では、裁判官が証拠開示に関する訴訟指揮をしないまま再審請求を棄却したが、その即時抗告審においては裁判官の訴訟指揮により213点もの未開示証拠の開示が実現した。
その上、第3次再審請求審では、検察官がそれまで「不見当ではなく不存在」と回答していた証拠も新たに発見され、検察官の回答が虚偽であったことが明らかとなった。
再審請求後の証拠開示についても、刑事訴訟法には明文の規定がなく、個々の再審請求事件を審理する裁判官が等しく証拠開示に向けた訴訟指揮が実現できるようにするために、証拠開示の法制化が必要である。
それゆえ、再審請求審において、請求人又は弁護人から証拠開示請求がなされたときは、裁判官は、特別の事情がない限り、検察官に対して、請求がなされたすべての証拠について開示に応じるよう勧告することを義務づける証拠開示制度を創設するべきである。
3 証拠目録の開示
再審請求審で、弁護側から証拠開示を求めたときに、検察官から「不見当」として、証拠開示を拒否され、裁判官からそれ以上勧告を出したり、検察官に対して釈明を求めたりできずに、証拠開示が進まないことがある。こうした事態への対抗策としても、証拠一覧表を開示する必要性は高い。再審請求審において、検察官は、捜査機関が保管する証拠(公判未提出のすべての証拠)について証拠目録を作成し、その証拠目録を開示する法制度を創設することが必要である。
4 証拠の保存の問題
有罪判決確定の前後を問わず、捜査機関に収集された証拠物について、所有者が所有権を放棄すると証拠物が処分ないし廃棄されるおそれがある。また、証拠物が還付されて被害者等に証拠物が返還されると、再審請求後に新たな鑑定を行って、新証拠の収集に努めようとしても、それができなくなってしまう可能性が高い。
判決確定後間もない段階で再審請求を行うというのは極めてまれであり、通常は長期間を経過した後に、再審開始決定の可否を検討してから再審請求が行われる。しかし、一般的に、公判未提出の証拠であるか否かを問わず、証拠物については保存期間の定めがなく、廃棄や還付の判断は検察官の裁量に委ねられている。そのため、公判未提出の証拠物の中に再審請求の決め手になるような証拠、たとえばDNA型鑑定の素材となる資料が証拠物に付着していても、証拠物自体の還付あるいは廃棄によって新証拠の発見が困難になる事態が現に生じている。その結果、再審開始決定を得るために有用な決定的証拠を失うということにもなりかねない。
現に大崎事件では、再審請求後に証拠開示を求めたが、その直前に共犯者の記録及び証拠(公判未提出証拠を含む)が廃棄されていたことが発覚し、未開示証拠が失われて取り返しのつかない事態となってしまった。このように証拠物保存の問題は、再審請求を行うに当たってはどの事件においても共通して生じる問題であり、本決議において特に取り上げる必要性の高いものである。
現行の検察官による恣意的な運用に歯止めをかけるためにも、再審請求を予定していることが明らかな場合には、本人の意思を確認して証拠物の保存を図るべきであり、証拠がなくなることで再審請求に支障が生じるような事態は極力回避すべく、現行の運用を改めるべきである。そして、最終的には証拠開示の法制化の中で、証拠の保存期間についても極力証拠を保存する方向で明文の規定を定めるべきである。
それゆえ、有罪判決確定の前後を問わず、再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者又はこれらの者の弁護人から再審請求の意向を示されたときには、検察官は、確定審において提出された証拠のみでなく、未提出の証拠についても保存する制度を設けるべく法制度を創設することが必要不可欠である。
第3 再審手続の長期化への対応策
1 再審請求手続中に元被告人が死亡した場合の承継手続の創設
再審開始決定さらに再審無罪判決を得るためには、多大な時間を要することになるのが一般的である。
松橋事件では、事件発生から再審開始決定の確定、さらには再審公判による無罪判決の確定まで、実に34年間の長年月を要した。その間に元被告人は高齢となり、現在は体調を崩して寝たきりの生活を送っている。
また、再審請求審で再審開始決定が出ても、検察官の即時抗告(又は異議申立て)がなされれば、審理が伸びることになるし、特別抗告がなされれば、さらに審理が長引くことになる。その間に元被告人が死亡すると、たとえ再審請求審で再審開始決定がなされたとしても、審理は終了するため、遺族等により再審請求を一からやり直さなければならなくなる。
これは再審手続に時間がかかりすぎることの弊害であり、再審請求中の元被告人が死亡した場合でも、遺族による再審請求手続の承継を可能とする法改正を行う必要がある。
2 再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止
松橋事件では、2012年(平成24年)に熊本地方裁判所に再審請求を行ってから、再審開始決定がなされるまで丸4年の年月を要した。
ところが、検察官は福岡高等裁判所に即時抗告し、その後即時抗告が棄却されると、最高裁判所に特別抗告を行った。そのため、審理の期間が伸び、最高裁判所で再審開始決定が確定するまで、さらに2年の年月を要した。特別抗告理由は憲法違反および最高裁判所の判例違反等に限定されているにもかかわらず、検察官による明らかに理由のない特別抗告により、再審開始決定の確定は大幅に遅れた。
元被告人の体調が悪化していく中で、何とか元被告人の生存中に再審開始が確定し、再審公判手続へと進むことができたものの、再審請求手続中も元被告人の健康状態は予断を許さない状態であった。かかる事態にまで長引いたことに対する検察官の責任は重大である。
また、大崎事件の第3次再審請求において、2017年(平成29年)6月に再審開始決定がなされ、検察官の抗告を受けた抗告審でも再審開始が維持されたにもかかわらず、検察官が特別抗告を行ったため、最高裁判所に1年3か月もの長期間係属した状態が続いた。この検察官の不服申立ては、いずれも事実認定の誤りを指摘するものにすぎず、適法な抗告理由を欠くものであり、再審を妨害する濫用的なものであった。
その結果、一刻を争う高齢の再審請求人の救済が不当に引き延ばされた上、検察官の特別抗告に理由がないとした最高裁判所が、不意打ち的に書面審査だけで原々決定及び原決定を取り消し、再審請求を棄却するという許しがたい事態が生じてしまった。
以上のような経過からすれば、今後再審開始決定に対する検察官の抗告禁止や異議申立禁止、特別抗告の禁止等、検察官の不服申立ての禁止のための法改正の必要がある。
第4 第三者機関による検証委員会の設置
1 再審無罪事件に関する検証の必要性
(1) 冤罪の原因としての自白偏重の問題点
捜査上の問題点として、客観的な証拠が乏しい状況で、捜査機関が自白を取ることに専念し、捜査機関としては被疑者から自白を取れば事件が解決したかのような風潮が見受けられる。
いきおい捜査機関は被疑者に無理な自白を迫るということが指摘できるし、長時間にわたる取調べや取調官による誘導が行われると、事実とは異なる虚偽自白がなされるおそれが高い。
そして、客観的な証拠がないところを被疑者の自白で補おうとするために自白が不合理に変遷することになる。
このような捜査機関による自白偏重の捜査について検証の必要性が高い。
(2) 証拠隠しの可能性
松橋事件では自白と矛盾する証拠が隠されていた可能性がある。凶器に巻き付け、その後燃やしたと自白した布が、実際には検察庁に証拠物として保管されていた。本来検察官としては起訴すべきではなかった事件であり、仮に確定審段階で自白と矛盾する証拠が提出されていれば、無罪になっていた可能性が高い。
大崎事件においても、公判未提出の証拠が早期に開示されていれば、2002年(平成14年)の第1次再審請求審において、鹿児島地方裁判所がした再審開始決定が確定していた可能性が高い。高齢の再審請求人は、検察官の証拠隠しにより長年の再審請求活動を強いられて、人生の長期間にわたり取り返しがつかないほどに無辜の救済を遅延させられている状況である。
その意味でも検察の捜査のあり方についても検証の必要性が高い。
(3) 事実認定における自白重視の問題点
一旦捜査段階で自白してしまうと、いくら公判で否認しても、裁判所には被告人の言い分を信用してもらえない傾向がある。
大崎事件では、再審請求をした元被告人は、共犯者とされる家族らの自白によって有罪判決が確定した。しかし、その自白は供述を行う能力に疑問のある、いわゆる供述弱者に対する配慮がないまま、厳しい取調べの結果、得られたものであった。
裁判官は事実認定において自白を偏重する傾向があり、客観的な証拠と捜査段階の自白とに矛盾があっても、捜査段階の自白にとらわれてしまいがちである。
また、不合理に自白が変遷していても、変遷の経過を仔細に検討することなく、本人の自白や共犯者の自白に信用性を認めてしまいがちである。この点は冤罪事件の特徴といっても過言でない。
その意味では裁判官の事実認定のあり方については、より慎重な姿勢が要求されるというべきであり、裁判官の事実認定についても検証の必要性がある。
(4) 弁護人の対応のあり方
被告人が捜査段階で自白し、膨大な自白調書が作成されているときでも、被告人が公判で全面的に否認したいという意向を示したときには、弁護人としては被告人の意向に従って公判で公訴事実を争うことを徹底すべきである。
弁護人の弁護活動のあり方についても検証の必要性が高い。
2 検証委員会による誤判原因の検証
再審無罪事件における以上の各問題点を踏まえ、国は再審開始決定が確定し、再審無罪となった事件について、誤判原因を検証するため、独立した第三者機関によって構成される検証委員会を速やかに設置すべきである。
ここでの検証委員会の性格は、捜査機関はもとより、裁判所を含めた関係機関からの独立性が保障され、十分な権限(調査権限を含む)を付与された公的な第三者機関とすべきである。
検証委員会の構成メンバーについては、(1)学者(刑事法、憲法、国際人権法、行政法等法学者、心理学、法医学者)、(2)法律実務家、(3)報道関係等の有識者、(4)誤判事件の救援に関わった市民(刑事人権団体構成員)、誤判事件の当事者等によるべきである。
調査権限としては、確定記録のほか、公判不提出の記録の提出を求め、証人喚問、証人尋問等を実施できる権限を与え、それを実行あらしめるため、関係機関等に対する強制調査権限を付与されるべきである。
また、関係機関に対して、誤判防止のための運用や制度の改善、改革を勧告、提言する権限を付与すべきである。
さらに、検証委員会においては、海外調査として、欧米諸国などの海外視察を実施したり、海外の誤判研究の専門家を招いてヒアリングを行うなど、誤判を産まない刑事司法のあり方について海外の実情を幅広く調査すべきである。
調査対象としては、過去10年間において再審無罪が確定した事件を対象とすべきである。
以上