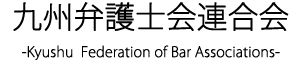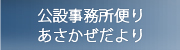「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に強く反対する理事長声明
法務大臣の私的懇談会である第7次出入国管理政策懇談会の下に設置された「収容・送還に関する専門部会」(以下「本専門部会」という。)は、2020年(令和2年)6月19日、「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」(以下「本提言」という。)を公表し、同年7月14日、法務大臣に対し、提出した。現在、出入国在留管理庁において、本提言を踏まえた出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の改正が検討されており、近々法案が提出される予定とされている。
しかし、当連合会は、本提言のうち、(1)退去等命令制度及び送還忌避罪等の創設、(2)難民申請者に対する送還停止効の例外の創設、(3)仮放免逃亡罪の創設に対して、強く反対する。
1 退去等命令制度及び送還忌避罪等の創設について
まず、本提言(29頁)は、送還促進措置として、退去強制令書の発付を受けた者(以下「被退去強制者」という。)に、渡航文書の発給申請等の命令制度・本邦からの退去命令制度とともに、これらの命令違反に対する罰則(送還忌避罪等)の創設を検討すべきとする。
しかしながら、法務省入国管理局「在留特別許可に係るガイドライン」(平成21年改訂)が「積極要素」として示すように、被退去強制者の中には、日本に実子や配偶者等の家族がいる者、日本で生まれ育った者や日本での滞在期間が長期間に及ぶ者など日本に定着し、本国との繋がりを失ってしまった者など、帰国困難な事情を抱える人々が存在する。従来、このような人々には在留特別許可が認められていたが、許可件数は2011年(平成23年)に6879人となった以降は減り続け、2019年(平成31年)は1481人と大幅に減少しており、審査の厳格化がうかがわれる。
それにもかかわらず、帰国困難者に対し刑罰による威嚇により帰国を強制することは、刑事施設と入管収容施設を行き来する状況を作り出すに過ぎず、実効性が乏しい上に、家族の保護等に関する憲法及び国際人権条約上の権利(世界人権宣言第15条第3項、自由権規約第23条第1項、社会権規約第10条第1項、子どもの権利条約第3条第1項、第9条第1項等)を侵害するおそれがある。特に、その中には、出入国在留管理関係訴訟(退去強制処分取消請求・難民不認定処分取消請求等)で国の敗訴が確定した判決が2016年(平成28年)から2018年(平成30年)までに26件存在することからも明らかなように、退去強制令書の発付等に対し行政訴訟を提起し司法手続を通じて在留が認められる人々も一定数存在するのであって、退去等命令制度及び送還忌避罪等の創設は、このような人々の裁判を受ける権利を奪うおそれもある。
また、このような罰則の創設は、当該外国人の家族や支援者、相談や依頼を受ける行政書士や弁護士などの活動が、共犯者として処罰されてしまう危険性が否定できず、少なくとも捜査機関による任意捜査や強制捜査(逮捕、捜索・差押え等)の対象となる危険性は十分にあるから、支援者等による人道的活動を萎縮させるおそれもある。そうなれば、脆弱な地位におかれた被収容者はますます孤立することとなる。
2 難民申請者に対する送還停止効の例外の創設について
また、本提言(34頁)は、難民認定申請手続の審査中には強制送還されない、いわゆる送還停止効(入管法第61条の2の6第3項)の定めについて、送還促進措置として、再度の難民認定申請者に対しては、一定の例外を設けることを検討するよう求めている。
しかしながら、我が国の難民認定率は、2011年(平成23年)以降、一次申請・不服申立の総認定率が1%未満であって、諸外国と比べて極端に低く、適切に機能しているとは到底いえない。また、日本において難民と認められた人々の中には、複数回申請を行い、裁判を経てようやく難民としての地位を認められた者又は人道的配慮から在留特別許可を認められた者も相当数存在する。
このように、本来難民として保護されるべき人々を十分に救済できていない現状において、送還停止効に対する例外を認めることは、本来保護されるべき難民を、迫害を受ける地域に送還してしまう危険性があるのであって、これを禁止する「ノン・ルフールマンの原則」(難民条約33条1項)を瓦解させる重大な危険性を孕んでいる。そして、このような例外の創設は、現在の実務上停止されている裁判中の送還にも波及するおそれがあって、司法手続により難民認定を求める人々の裁判を受ける権利を侵害するおそれがある。
3 仮放免逃亡罪の創設について
さらに、本提言(54頁)は、収容の在り方として、被退去強制者のうち仮放免された者の逃亡等の行為に対する罰則(仮放免逃亡罪)の創設を検討するよう求めている。
しかしながら、現行法においても、仮放免中の逃亡には保証金の没取等の措置が設けられており、かつ、一定期間おきに出入国在留管理局への出頭を求め、延長している実態に照らせば、さらに刑罰を科さなければならない立法事実が十分に検討されているとはいえない。そもそも収容は逃亡のおそれがある場合にのみ認められるのであって、被退去強制者を全て収容する「全件収容主義」自体が問題であり、収容は最後の手段でなければならないことから、逃亡に罰則を科すことはこの趣旨と矛盾している。
また、退去等命令制度及び送還忌避罪等と同様に、被仮放免者が逃亡した場合、仮放免許可申請に関与した弁護士や身元保証人となった支援者等が、共犯者として処罰されてしまう危険性が否定できず、捜査機関の任意・強制捜査の対象となる危険性は十分にあり、仮放免許可自体への支援を萎縮させるおそれもある。
4 長期収容問題を解消するために
従来、法務省は、収容が長期化している案件については弾力的に仮放免を活用するとしていたが、2015年(平成27年)ころから、この運用を転換し、仮放免許可の運用の厳格化等を指示し、とりわけ、2018年(平成30年)2月28日付法務省入国管理局長指示「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の更なる徹底について(指示)」を発し、仮放免許可の運用の厳格化を進め、長期収容が増加した。
そのような状況の中、2018年(平成30年)4月13日、東日本入国管理センターにおいて、仮放免申請が前日に却下されたインド国籍の男性が死亡する事件が発生した。また、2019年(平成31年)ころから抗議のため多くの被収容者たちが正に命と引き換えにハンガーストライキを始め、同年6月24日には、大村入国管理センターにおいてナイジェリア国籍の男性が餓死するという事件が発生し、本専門部会の設置に繋がった経緯がある。このように入管長期収容によって生命が奪われるという悲劇は決して繰り返されてはならない。
当連合会においても、2019年(令和元年)10月29日付「大村入管センターにおけるナイジェリア人死亡事案に関する調査報告書に対する理事長声明」において、入管長期収容に関する現在の誤った運用を抜本的に見直すこと等を求めてきたところであるが、長期収容問題を解消するための入管法改正としては、被退去強制者の「全件収容主義」を改め、収容は逃亡のおそれがある場合に限定するとともに、収容の開始時又は継続時における司法審査及び収容期間の上限を導入すること等の措置を講じることこそがまずもって検討されるべきである。
2020年(令和2年)9月11日
九州弁護士会連合会
理事長 内田 光也